研究者の営みと市民とをつなぐ
バランスのとれた認識を共有する
News & Topics
ユーラシア研究所とは

ユーラシア研究所は、ソ連におけるペレストロイカのさなかの1989年1月、ソビエト研究所として設立され、1994年にユーラシア研究所と改称して今日に至っています。
ロシアはその魅力的な文学や音楽などの文化によって、古くから多くの人々を引きつけてきました。同時にロシアやソ連は、革命、社会主義、戦争、改革と解体など世界史的に見て大きな出来事に満ちており、それぞれの関心から熱い視線が注がれてきました。またロシアは、領土問題を含むさまざまな接点をもった隣国のひとつであり、隣国としての良好な関係を維持する特別な必要性のある国でもあります。
今日では、旧ソ連諸国を「ユーラシア地域」として一体的にとらえることは妥当かを問わざるを得ないさまざまな変動が生じています。また、この地域は他の地域から孤立して存在しているのではなく、近隣地域をはじめ、流動的な世界の中にあることは言うまでもありません。「ユーラシアとは何か」ということ自体、さまざまな答えのありうる“問い”のひとつです。
ユーラシア研究所は、このようなユーラシア地域について、「研究者の営みと市民とをつなぐ」、「バランスのとれた認識を共有する」という理念のもとで活動しています。〈ユーラシアについてともに学び研究するプラットフォーム〉―それがユーラシア研究所です。
 ユーラシア研究所 最新出版物情報
ユーラシア研究所 最新出版物情報
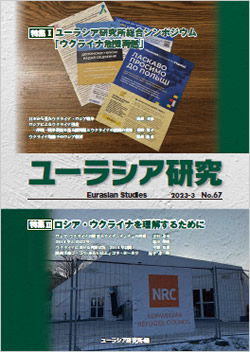
ユーラシア研究 67号
- 出版社
- 群像社
- 発売日
- 2023年3月30日
- ムック
- 80ページ
- 特集
- Ⅰ:ユーラシア研究所総合シンポジウム「ウクライナ危機再燃」
Ⅱ:ロシア・ウクライナを理解するために


 最近のセミナー・シンポジウム情報
最近のセミナー・シンポジウム情報

